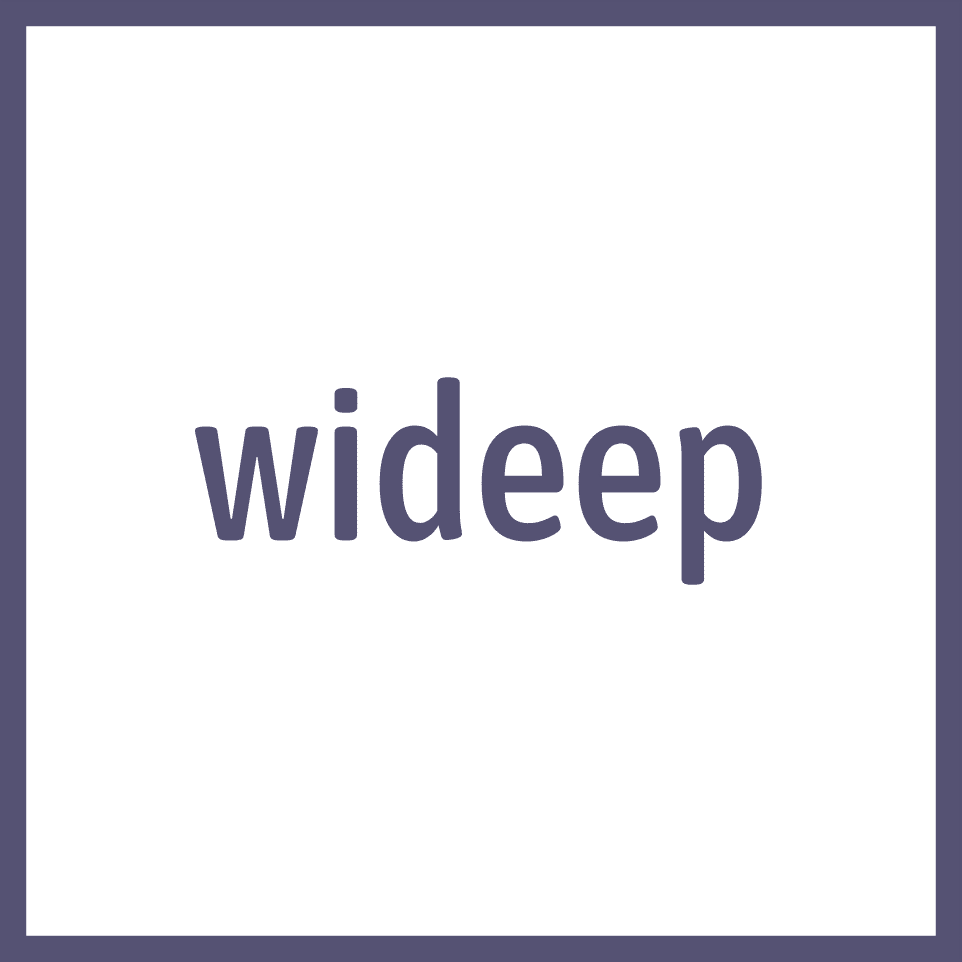こんな方におすすめ
- スーパーや直売所でカナガシラを見かけたけど「どうやって料理するの?」と迷っている人
- カナガシラを店頭で扱っているけれど、消費者にどう伝えたら良いか悩んでいる人
- カナガシラを釣ったけれど「食べられるの?」「美味しい調理法は?」と調べている人

wideepについて
wideepでは水産専門のwebコンサルを行っております。
水産業の現場を解っているから、『話すだけ』『見せるだけ』で貴社の魅力や課題解決をご提案いたします。
wideepについて詳しくはこちらをご覧ください
カナガシラとは?基本情報
カナガシラは見た目がホウボウにそっくりな魚で、知名度はあまり高くありません。
しかし、その白身は淡白で上品な味わいがあり、家庭料理や漁師めしとして昔から食べられてきました。
ここでは、カナガシラの学名や分類、生息している場所、旬の時期などを紹介していきます。
カナガシラの分類と学名
カナガシラはスズキ目ホウボウ科に属する魚です。
学名は Lepidotrigla microptera と呼ばれ、体長は20〜30cmほど。

分類上はホウボウの仲間なので、料理法や味わいも似ているのが特徴です。
生息している海域と漁獲エリア
カナガシラは日本各地の沿岸部に広く分布しています。

漁獲は底引き網漁や定置網漁でとれることが多く、特に東北や北陸の漁港でよく水揚げされます。
スーパーに並ぶことは少ないですが、産地の市場や朝市では比較的よく見かけます。
旬の時期と流通量の特徴
カナガシラの旬は秋口から春にかけてといわれています。

ただし流通量はそれほど多くなく、都会のスーパーで見かける機会は少なめです。
カナガシラの特徴
カナガシラは赤っぽい体に大きな胸びれがある、ちょっとユニークな見た目の魚です。
見慣れない人にはホウボウと間違われることが多いですが、よく観察すると違いがわかります。
ここでは体の特徴やホウボウとの違い、そして地域ごとの呼び名について紹介します。
体の色や形の特徴
カナガシラの体は鮮やかな赤色からオレンジ色をしています。
体長は15〜30cmほどで、細長い体に大きな胸びれがついているのが特徴です。
この胸びれは海の底を歩くように動かすことができ、餌を探すときに役立ちます。
また頭の骨が硬いことから「金頭(カナガシラ)」という名前がついたとも言われています。
ホウボウとの違い
カナガシラはよくホウボウと混同されますが、実際には別の魚です。

またホウボウの胸びれの内側は青や緑の模様が鮮やかですが、カナガシラは全体的に赤っぽい色合いで模様が少ないです。
サイズと色味を見れば、両者を見分けることができます。
地域ごとの呼び名(別名・方言名)
カナガシラは地方によってさまざまな名前で呼ばれています。
関西では「カナ」や「ガシラ」と呼ばれることもあり、東北では「ガラ」や「エンマ」といった方言名が使われることもあります。
同じ魚でも地域によって呼び名が変わるのは、日本の魚文化の面白いところです。
旅行先や市場で名前が違っても、実はカナガシラだったということも珍しくありません。
カナガシラの食べ方・料理法
カナガシラはクセのない白身で、和食から洋食まで幅広い料理に使える魚です。
煮付けや唐揚げといった定番から、ちょっと工夫した洋風レシピまで応用できるのが魅力。
ここでは調理の定番法やコツに加えて、実際に魚屋さんからいただいた調理アイデアも紹介します。
定番の食べ方:煮付け・唐揚げ・味噌汁
カナガシラは身がやわらかいため、煮付けにすると味が染み込みやすく、ご飯のおかずにぴったりです。
唐揚げにすると骨ごとカリッと食べられるので、小骨が気になる人にもおすすめ。
さらにアラから旨みが出る味噌汁は、漁師町の家庭料理としてもおなじみです。
鮮魚店さんからはこんな声をいただきました。
- 魚屋さんの声①
「刺身、昆布〆、アクアパッツァ、味噌汁が美味しい!」
下処理のコツと小骨対策
カナガシラは小骨が多いため、三枚おろしにしたら骨抜きでしっかり取り除くのがポイントです。
また、揚げ物にすれば骨がやわらかくなり、そのまま食べやすくなります。
鮮度が落ちやすい魚なので、買ったらすぐに下処理するのがおすすめです。
臭みを消したいときは軽く塩を振ってから調理すると、身の旨みが引き立ちます。
- 魚屋さんの声②
「フライとか天ぷら、ムニエルも美味しいですよ!」
淡白な味わいを活かしたおすすめレシピ
カナガシラは淡白な味わいなので、和洋どちらの料理にも使えるのが魅力です。
シンプルに塩焼きにしてレモンを絞ると、身の甘さがストレートに感じられます。
洋風ならアクアパッツァやブイヤベースに入れるとスープが濃厚になり、家庭でもレストランの味を楽しめます。
バターを使ったムニエルや、昆布〆にしておつまみにするのもおすすめです。
カナガシラの市場価値
カナガシラは漁港ではよく水揚げされる魚ですが、一般のスーパーではあまり見かけません。
実は安価で手に入りやすいにもかかわらず、知名度が低いため「地元で消費される魚」という位置づけになっています。
ここでは、カナガシラが市場でどう扱われているのか、購入時のポイントまで解説します。
スーパーでは見かけにくい理由
カナガシラは漁獲量が安定せず、地域限定で水揚げされることが多い魚です。

地元の人には馴染みがありますが、都会ではほとんど流通していません。
そのため「知る人ぞ知る魚」として、主に漁師町や直売所で食卓に並ぶことが多いのです。
漁港や直売所での価格相場
カナガシラは市場価値としては比較的安価で取引されています。
漁港や直売所では1匹100円〜300円程度で売られることもあり、まとめ買いされるケースもあります。
ただし鮮度が落ちやすい魚なので、値段よりも水揚げされたばかりかどうかが重要です。
都会の鮮魚店や専門店では流通量が少ない分、少し高めに売られることもあります。
カナガシラを美味しく食べるための購入ポイント
カナガシラを買うときは、目が透き通っていてエラが鮮やかな赤色をしているものを選びましょう。
体表がつやつやしていて張りがあるものは鮮度が高い証拠です。
また、できれば漁港や朝市で購入するのがベスト。

普段スーパーでは出会えない魚だからこそ、見つけたときはぜひ手に取ってみてください。
まとめ|カナガシラは身近で美味しい旬の魚
カナガシラは知名度こそ高くありませんが、冬から春にかけて旬を迎える美味しい魚です。
淡白で上品な味わいは煮付けや唐揚げ、味噌汁などさまざまな料理で楽しめます。
ホウボウと間違えられることも多いですが、特徴を知れば違いも一目でわかります。
スーパーではあまり見かけませんが、漁港や直売所では安価で手に入ることもあります。

知る人ぞ知る「隠れた名魚」として、見かけたらぜひ食卓に取り入れてみてください。
カナガシラをもっと売りたい魚屋さん・水産会社は水産専門Webコンサルwideepへ!
カナガシラをはじめ旬の魚をもっと知ってほしい、もっと売りたいと感じていませんか?
SNSやホームページで発信しても「なかなか集客につながらない…」という声をよく聞きます。

まずは無料診断からお気軽にどうぞ。
▶︎ 水産専門Webコンサル wideepはこちら