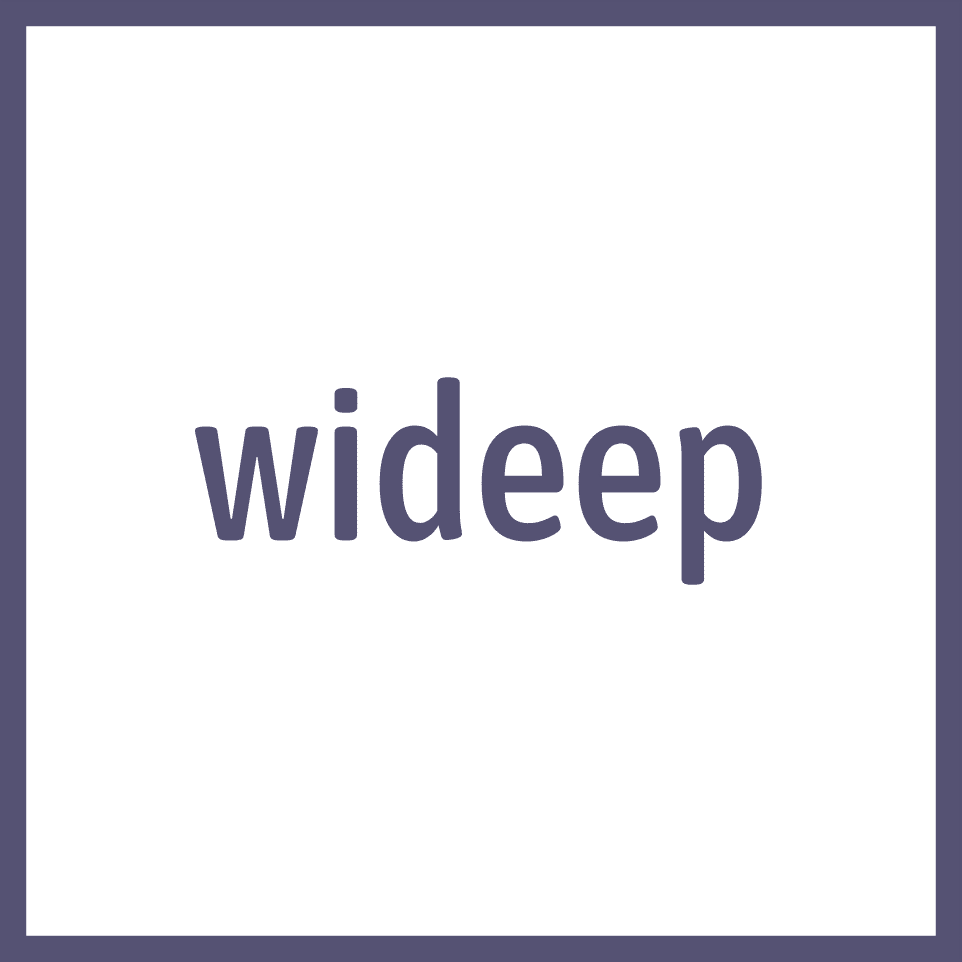こんな方におすすめ
- 魚の扱いには慣れているが、店舗経営は初めての人
- 開業に必要な許可や資金、準備の流れを一から知りたい人
- Web通販(EC)も視野に入れて販路を広げたいと考えている人

wideepについて
wideepでは水産専門のwebコンサルを行っております。
水産業の現場を解っているから、『話すだけ』『見せるだけ』で貴社の魅力や課題解決をご提案いたします。
wideepについて詳しくはこちらをご覧ください
海鮮専門店の開業に必要な許可・資格とは?

海鮮専門店を始めるには、ただ魚を仕入れて調理すればいいわけではありません。
飲食店営業に必要な許可や、魚介類を扱う場合の追加許可など、法律的な準備が欠かせません。
ここでは、開業前に押さえておきたい基本的な手続きについて解説します。
飲食店営業許可の取り方
まず必要なのが『飲食店営業許可』です。
店舗の構造や厨房の設備、衛生基準などを満たしていなければ取得できません。
開業地を管轄する保健所に事前相談を行い、工事前に内容をすり合わせておくことがスムーズな取得への第一歩です。
申請から許可が出るまでに1〜2週間ほどかかるため、スケジュールには余裕を持って動きましょう。
魚介類を扱うための追加許可
生の魚介類を提供・販売する場合、『魚介類販売業』や『食品の小分け業』などの追加許可が必要になることがあります。
このあたりのルールは自治体によって異なるため、保健所での確認が必須です。

場合によっては、調理工程や保管方法の指導が入るケースもあるので、事前準備はしっかりと。
保健所や消防署への届出も忘れずに!
飲食店を開業する際には、保健所への営業許可申請だけでなく、火を扱う設備がある場合は消防署への届出も必要です。
厨房の防火設備や避難導線の確保など、安全基準を満たしているかをチェックされます。
特に都市部では審査が厳しくなる傾向があるため、設計段階から確認をしておくと安心です。
海鮮専門店の開業初期費用はどれくらい?内訳と目安


海鮮専門店の開業には、思った以上にコストがかかります。
特に物件取得費や厨房設備、内装工事などはまとまった資金が必要です。
ここでは主な費用の内訳を見て、どのくらいの準備が必要かを把握しましょう。
物件取得費・内装工事費・設備費
物件取得費として、家賃の数ヶ月分の前払いに加え、保証金・礼金などが必要です。
さらに、内装工事や厨房機器、テーブルや椅子などの設備にかかる費用が数百万円単位になることも。

初期費用のなかでも大きなウェイトを占める部分です。
厨房機器や冷蔵・冷凍設備にかかる費用
鮮度が命の海鮮を扱うには、業務用の冷蔵庫や冷凍庫が不可欠です。

これらは新品で揃えると高額になりますが、中古品を上手く活用すればコストを抑えることも可能。
保健所の指導に従い、清掃性の高い設備を選びましょう。
フランチャイズの場合の加盟金や運転資金
海鮮丼などのフランチャイズに加盟する場合、
- 加盟金
- 保証金
- 研修費
- ロイヤリティ
が発生します。
加えて、運営開始後の原材料費、人件費、光熱費などを6ヶ月程度見込んだ「運転資金」も必要です。
予想外の出費に備えて、資金計画には余裕を持たせておくことがポイントです。
資金ショートを防ぐには、この項目が最重要です。
安心・安全な海鮮提供のための衛生管理ポイント

生ものを提供する海鮮店では、衛生管理が何よりも大切です。
トラブルや食中毒を防ぐためにも、開業前からルール作りを徹底しましょう。
- 生ものを扱うなら温度管理が命!
- 調理器具の洗浄・区分の徹底
- HACCP(ハサップ)対応とその簡易導入
ここでは基本となる3つのポイントを紹介します。
生ものを扱うなら温度管理が命!
刺身や寿司ネタなどの生魚は、10℃以下での保存が基本です。
届いたネタをすぐに冷蔵保存し、提供直前まで常温にさらさないことが重要です。

温度計の導入や記録シートの活用も有効です。
調理器具の洗浄・区分の徹底
魚を扱う包丁やまな板と、野菜用・肉用などはしっかり分けましょう。
交差汚染(クロスコンタミ)を防ぐために、色分けや器具のラベリングが効果的です。

清掃ルールは従業員にマニュアル化して共有すると◎。
HACCP(ハサップ)対応とその簡易導入
2021年から、すべての食品事業者にHACCP対応が義務化されました。
とはいえ個人店舗では簡易HACCPの対応でOKです。

無料で使えるテンプレートなどもあるので、導入を検討しましょう。
店舗の立地選びとコンセプト設計のコツ

海鮮専門店といっても、立地やコンセプトで集客力は大きく変わります。
自分のお店の“強み”をしっかり定めた上で、立地との相性を見極めましょう。
どんな客層を狙うかを明確にする
まずは「誰に食べてもらいたいのか」をはっきりさせましょう。
- サラリーマン向けのランチ営業?
- 家族連れのディナー?
- 観光客向け?
ターゲットを絞ることで、提供するメニューや価格帯、内装デザインも自然と決まってきます。
ターゲットがブレないお店は、ファンも付きやすくなります。
「テイクアウト特化」「昼営業中心」など差別化例
最近では「海鮮丼テイクアウト専門店」や「昼だけ営業する海鮮定食屋」など、業態を絞ったお店も人気です。

差別化のアイデアがしっかりしていれば、競合の多い地域でも存在感を出せます。
商業施設内・住宅街・観光地…どこがいい?
駅前や商業施設内なら集客力は高いですが、家賃も高めです。
住宅街なら地元の常連を確保しやすく、観光地なら土日祝の売上が見込めます。

周囲の競合店の調査も忘れずに。
仕入れルートはどうする?安定した仕入先の見つけ方


海鮮店の命は「仕入れ」にあり!
鮮度・価格・安定供給を実現するには、信頼できる仕入れ先の確保が欠かせません。
- 地元の市場・漁港との契約
- 鮮魚仲卸業者の選び方
- 配送対応と冷蔵管理の体制づくり
ここでは代表的な仕入れ先と、注意すべきポイントを紹介します。
地元の市場・漁港との契約
地元の市場や漁協から直接仕入れる方法は、鮮度の高い魚を手に入れられる大きなメリットがあります。
また、地域の特産品や旬の魚を活かすことで“地元愛”を打ち出すブランディングも可能です。
顔の見える仕入れ先との関係性は、長く続くお店づくりにおいて非常に重要です。
鮮魚仲卸業者の選び方
仲卸業者を通じた仕入れは、種類が豊富で配送面の安心感もあります。
特に忙しい店舗運営では、安定的に魚を届けてくれる業者が強い味方になります。
複数の業者を比較して、
- 価格
- 品質
- コミュニケーションのとりやすさ
のバランスが取れた取引先を選びましょう。
見学や試験仕入れをお願いするのもアリです。
配送対応と冷蔵管理の体制づくり
遠方から仕入れる場合は、クール便や冷凍便(もしくは市場便)の活用が前提になります。
また、自店舗側でも受け取り〜保管〜提供までの流れで冷蔵・冷凍の設備が整っているかが重要です。
仕入れと保存の両面で「温度が管理されているか」を意識することで、品質トラブルを防げます。
創業計画書と資金調達の準備

開業に向けた行動を加速させるには、事業の“設計図”ともいえる創業計画書の作成がカギになります。
合わせて、資金調達の方法も早めに整理しておきましょう。
創業計画書に書くべきポイント
創業計画書には「事業の目的・ターゲット・商品・収支計画・運営体制」などを明記します。
とくに、銀行や公庫に提出する際は、“再現性のある数字”を示すことが信頼につながります。
最初から完璧を目指さず、まずは書いてみることがスタートです!
日本政策金融公庫や銀行での借入方法
日本政策金融公庫では、無担保・無保証人で最大2,000万円の融資が可能なケースもあります。
自己資金が3〜5割ほどあると、審査も通りやすくなります。

申請には計画書と必要書類の準備が必要です。
補助金や助成金の活用も検討を!
小規模事業者持続化補助金や、各自治体の創業支援助成金なども狙い目です。
補助金は「後払い」が多いため、先に資金を用意する必要はありますが、設備や広告費の支援に役立ちます。
公的支援制度の情報は定期的にチェックしましょう。
開業までのスケジュールとやるべきこと一覧
 

開業は一大プロジェクト。
勢いだけで始めると準備不足になりがちなので、しっかりスケジュールを立てて進めましょう。
開業までにかかる期間はどのくらい?
物件探しから許可取得、設備工事などを含めると、少なくとも6ヶ月は見ておくと安心です。

とくに保健所の許可申請は時期によって混み合うので早めの行動が大切です。
段階ごとのタスクとスケジュール管理
大まかには「準備段階」「設備・工事段階」「開業前広報段階」に分かれます。

やり残しを減らせるだけでなく、開業の不安も軽減されます。
トラブルを減らすためにやっておきたい準備
仕入先・工事業者・許可申請など、関係者が多い開業準備では、行き違いや遅延が起きやすいです。
契約内容や期日を明文化し、トラブルを未然に防ぐ意識を持ちましょう。
また、予備日や予算の余裕を持たせておくと安心です。
Web販売も視野に入れると広がる可能性!


実店舗だけでなく、オンラインでの販売にも注目が集まっています。
海鮮を扱うからこそ「地方の特産を全国へ」届けるチャンスも。
ここではWeb販売の基礎と可能性を紹介します。
海鮮通販の需要が伸びている理由
共働き世帯や高齢化の影響で、「自宅で美味しい魚を食べたい」というニーズが増えています。

地方の海産物やブランド魚を、手軽に取り寄せられるサービスは人気です。
口コミやSNS経由の注文も増えており、実店舗と違った可能性が広がっています。
ネット販売に必要な設備と許可
魚介類をネットで販売する場合も、保健所からの許可が必要になります。
特に冷凍・冷蔵での発送が基本になるため、クール便対応の設備や梱包資材が欠かせません。
加えて食品表示や賞味期限ラベルなども必要です。
安心して食べてもらうための体制づくりは、信頼につながります。
自社EC/モール出店の違いと向き不向き
ネット販売には「楽天・Yahoo!・食べチョク」などのモール型と、「BASE・STORES」などの自社EC型があります。
モール型
集客力がある
テンプレが豊富で楽
お金がかかる
EC型
最初は大変
試行錯誤が必要になりやすい
利益率が高い
運営費用が安い
売上が安定するとサイト自体が財産になる

最初はモールからスタートするのも一案です。
開業後に差がつく!集客・リピーター獲得の方法


良いお店を作っただけではお客さんは来ません。
しっかり集客して、リピーターにつなげていくことが成功のカギになります。
ここでは開業後の実践的な対策を紹介します。
GoogleマップやSNSの活用法
まずやるべきは「Googleビジネスプロフィール」への登録!
地図検索での表示順位が上がり、口コミも投稿されやすくなります。
また、X(旧Twitter)やInstagramで“おいしそうな写真”を投稿するのも効果的。
近隣の人に届くよう、ハッシュタグや位置情報も活用しましょう!
常連をつくる仕掛けと接客の工夫
一度来てくれたお客さんが「また来たい!」と思ってくれる仕組みを作りましょう。
例えば、ポイントカードやLINEクーポンの導入、小鉢サービスなど“ちょっと嬉しい体験”がリピートのカギになります。
お客さんの名前や好みを覚えるなど、接客も大事な差別化ポイントです。
店舗とECのクロスプロモーションで売上アップ
店舗に来たお客さんに「ネット通販もやってます」と伝えることで、購買のきっかけが増えます。

ECと店舗をうまく連携させて、売上を底上げしていきましょう。
海鮮開業で失敗しないために!“魚のプロ×Webのプロ”に相談してみませんか?
 

開業は「やりたい!」という気持ちだけでは成功しません。
許可・資金・集客・ECなど、やることは山ほどあります。
そんなときこそ、信頼できる相談先があると安心です。
私は水産業に特化したWebコンサルティングを行っています。
- ホームページ制作
- 通販サイトの立ち上げ
- SNS集客
- 補助金のサポート
など、海鮮に強い視点でサポート可能です。
「鮮度やこだわりはあるけど、うまく伝えられない…」そんな悩みを一緒に解決しませんか?